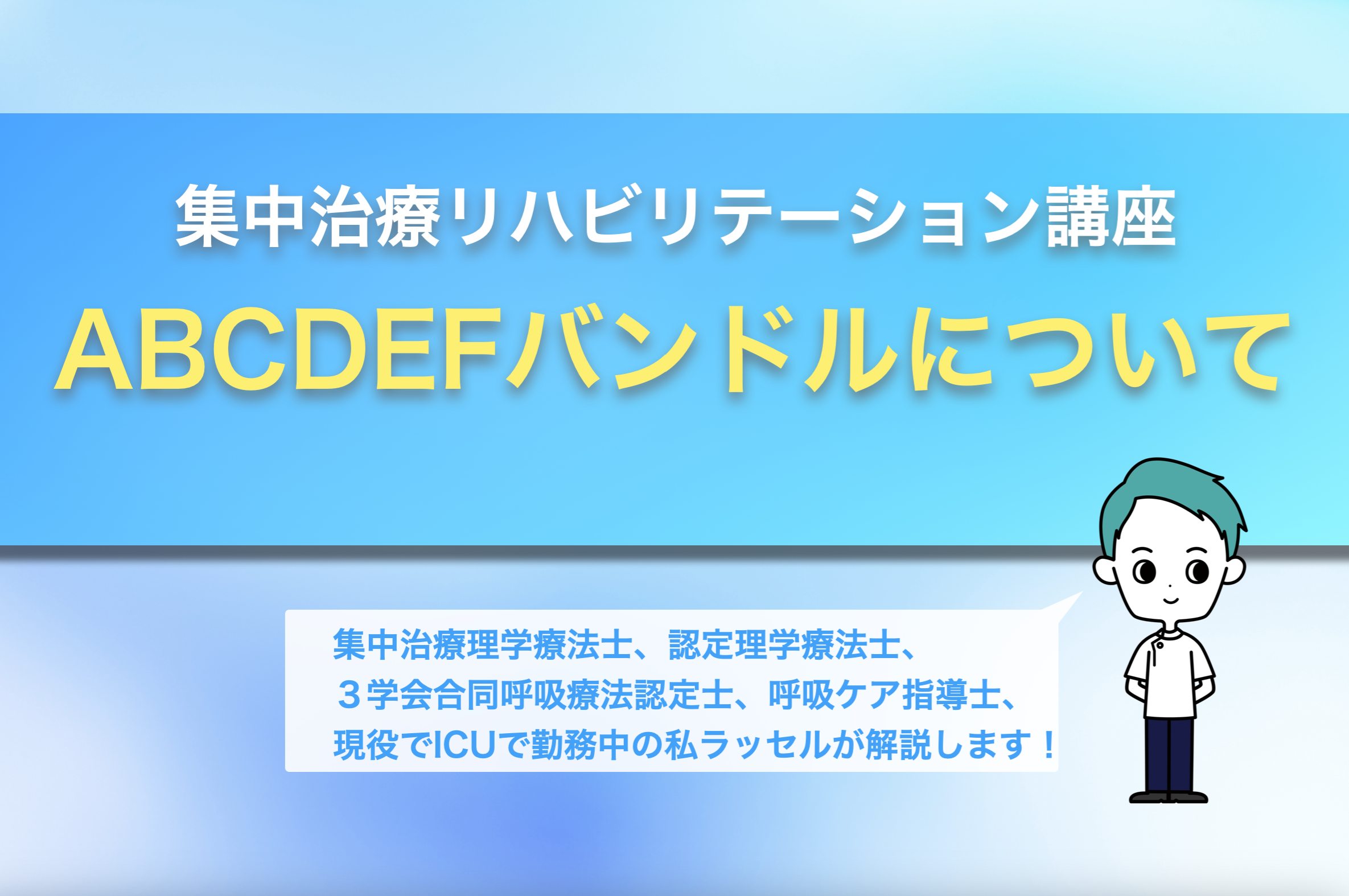ABCDEFバンドルとは、集中治療室(ICU)において、重症患者に対するケアを体系的に整理した「具体的な実践手順」であり、いわば医療チーム全体の共通言語となるフレームワークです。
このバンドルに基づいて、医師・看護師をはじめ、リハビリテーションスタッフ、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーなど、さまざまな職種が連携しながら、毎日どのようなケアを提供していくかを確認・実行していきます。
“ABCDEF”という英単語の一文字一文字が、それぞれ重要なケア項目を示しており、それらを日々実践していくことで、せん妄の予防や人工呼吸器からの早期離脱、死亡率の低下といった、患者さんの予後改善につながることがわかっています。
この記事では、このABCDEFバンドルが具体的にどのような内容なのか、そしてなぜこれがICUケアにおいて重要なのかを掘り下げていきます。
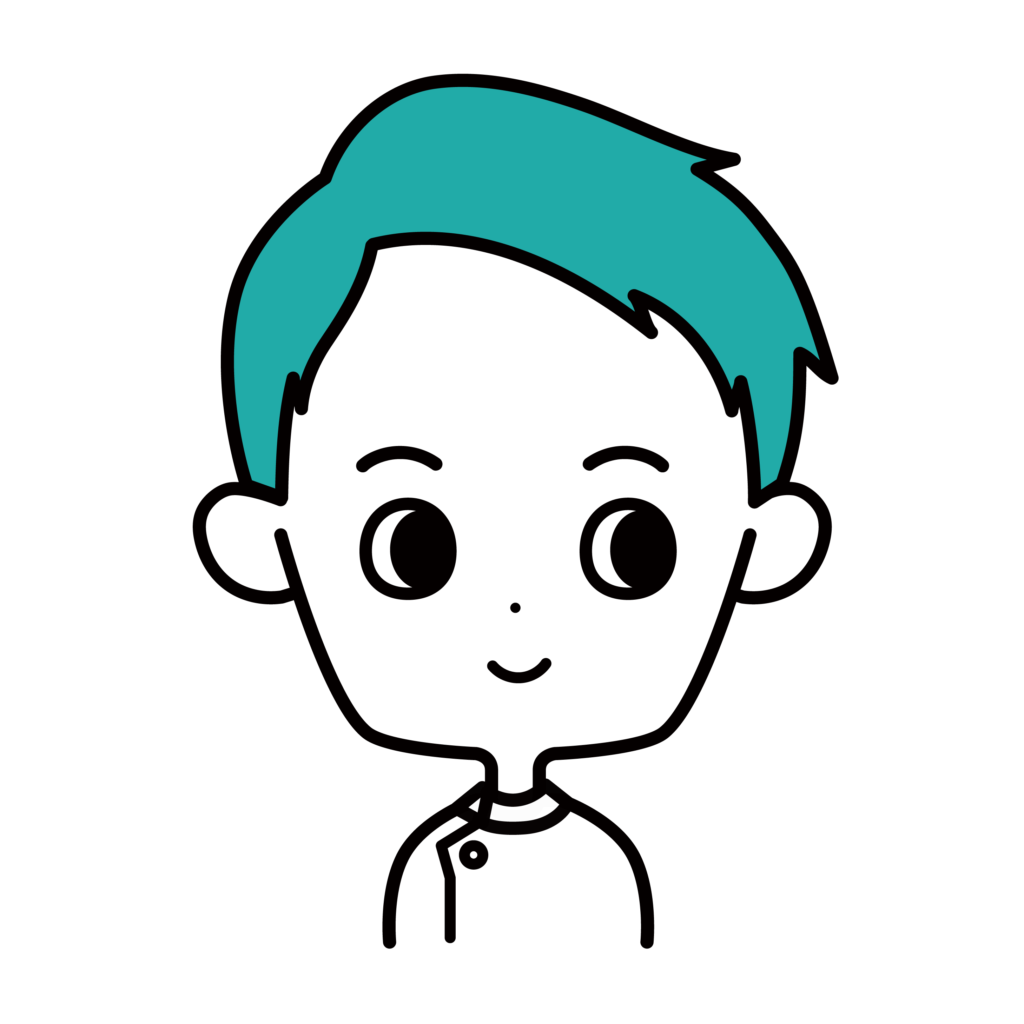
- 臨床19年目の現役理学療法士
- 認定理学療法士(呼吸)、集中治療理学療法士、3学会合同呼吸療法認定士、呼吸ケア指導士
- 集中治療室、救命救急病棟、一般病棟にて呼吸器疾患、重症疾患患者さんの治療に日々奮闘中
- 医療の最前線から本当に必要な情報を発信します
ABCDEFバンドルの概要
ABCDEFバンドルとは、ICU患者のアウトカム改善を目的に、多職種による標準化された包括的ケアを体系化したものであり、次の6つの要素から構成されます:
- A: 痛みの評価・予防・管理(Assess, prevent, and manage pain)
- B: 自発覚醒・自発呼吸トライアルの実施(Both SAT and SBT)
- C: 鎮痛・鎮静薬の最適な選択(Choice of analgesia and sedation)
- D: せん妄の評価・予防・管理(Delirium: assess, prevent, and manage)
- E: 早期離床・運動(Early mobility and exercise)
- F: 家族の関与と支援(Family engagement and empowerment)
せん妄の発生率低下1)、人工呼吸器装着期間の短縮2)、ICU滞在日数の短縮3)、死亡率の低下4)といった、患者にとって重要なアウトカムの改善がABCDEFバンドルにより報告されています。
また、多職種の協働とケアの質の標準化を通じて、患者満足度や家族の心理的サポートの向上にも寄与するとされており5)、世界中の集中治療領域で広く推奨されているケア指針のひとつです。
A:Assess, prevent, and manage pain 痛みの評価・予防・管理
集中治療を受ける患者さんは、意識がはっきりしている場合だけでなく、意識が低下している場合でも、何らかの痛みを抱えていることが多いと言われています。
人工呼吸器やチューブ、処置や検査など、ICUの環境自体が痛みを引き起こす要因になるため、痛みの「見逃し」が大きな問題になります。
そのため、ABCDEFバンドルでは最初の“A”として、「痛みを評価し、予防し、適切に管理すること」が強調されています。
なぜ痛みの評価・予防・管理が重要か?
- 痛みが放置されると…
- 呼吸・循環への悪影響(ストレス反応)
- 睡眠障害やせん妄のリスク上昇
- リハビリテーションの妨げになる
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)など退院後の影響も
痛みの評価・予防・管理のために何をするのか?
- 評価:患者の意識レベルに応じて、適切な評価スケールを使う
例)NRS(Numerical Rating Scale)、VAS(Visual Analogue Scale)、BPS(Behavioral Pain Scale)、CPOT(Critical Care Pain Observation Tool)など - 予防:あらかじめ処置に合わせて鎮痛薬を投与するなど、先手を打った対応も含まれます
- 管理:鎮痛薬の選択、持続投与・レスキュー投与の調整、非薬物療法の併用など
現場で意識すべきこと
- 「痛みを訴えなければ痛みがない」とは限らない
- 意識がないからといって無痛ではない
- 看護師・リハビリテーションスタッフ・医師が共通の評価方法で痛みを捉えることが重要
- 鎮痛が不十分だと、それ以降のB以降の項目(覚醒・運動)にも影響する
理学療法士として痛みをどう捉えるか
理学療法士としては、後述するE:Early Mobility and Exercise 早期離床と運動の促進において、疼痛のコントロールが重要となります。
離床を進めるにあたっては、重症患者リハビリテーション診療ガイドライン20236)にて離床開始基準が示されています。このガイドラインでは、離床を開始するにあたり以下の疼痛コントロールが推奨されています。
- 自己申告可能な場合:NRS ≤ 3 または VAS ≤ 30 mm
- 自己申告不能な場合:BPS ≤ 5 または CPOT ≤ 2
- 耐えがたい痛みや苦痛の訴えがない
B:Both Spontaneous Awakening Trials and Spontaneous Breathing Trials 自発覚醒トライアル(SAT)と自発呼吸トライアル(SBT)の両方の実施
この「B」は、人工呼吸器を使用している患者さんの離脱を早めるための重要なステップです。
鎮静が深すぎたり、人工呼吸器への依存が長引いたりすると、せん妄や筋力低下(ICU‑AW)、ICU滞在の長期化につながるため7)8)、意図的に「覚醒」と「自発呼吸」を試す時間をつくるという考え方です。
SAT:Spontaneous Awakening Trials:自発覚醒トライアルとは?
- 一時的に鎮静薬の投与を中止または減量し、患者がどの程度覚醒できるかを確認する
- 呼びかけに反応するか、混乱の兆候があるか、安全に覚醒できるかを評価
SBT:Spontaneous Breathing Trials:自発呼吸トライアルとは?
- 人工呼吸器のサポートを最低限にして、患者が自分で呼吸できるか確認する
- CPAPやTピースモードなどで、短時間の試験的呼吸を行い、離脱の可能性を見極める
なぜSATとSBTをセットで考えるのか?
- 鎮静が深ければ呼吸状態の正確な評価ができない
- 覚醒が不十分だと抜管後のリスクが高まる
- 逆に、適切なタイミングでSATとSBTを行うことで、抜管のチャンスを逃さず、早期離脱が可能になる
実践のポイント
- 毎朝のICU回診などで「今日SAT・SBTができるか?」を判断
- 呼吸状態・循環動態・鎮静深度を総合的にチェック
- 看護師・医師・呼吸療法士・リハビリテーションスタッフが連携して安全に進める
C:Choice of Analgesia and Sedation 鎮痛・鎮静薬の適切な選択
ABCDEFバンドルの「C」では、痛みと鎮静のバランスをどうとるかがポイントです。
ICUでは、処置や不快感に対して鎮痛・鎮静を行うことが一般的ですが、鎮静が深すぎたり、人工呼吸器への依存が長引いたりすると、せん妄や筋力低下(ICU‑AW)、ICU滞在の長期化につながることが知られています9)10)。
そのため、「C」では”必要最小限で質の高い鎮痛・鎮静”を選ぶこと”が求められます。
なぜ鎮痛・鎮静薬の適切な「選び方」が重要なのか?
- 過鎮静(Deep Sedation):意識消失状態に近く、せん妄やICU-AW(筋力低下)リスクが増加
- 過軽鎮静(Undersedation):痛み・不安がコントロールされず、ストレス反応や自己抜管の危険性
- 薬剤の特性によってせん妄や覚醒遅延のリスクが異なる
適切な鎮静レベルとは?(RASSスケールでの推奨)
RASS(Richmond Agitation-Sedation Scale)は、−5(完全に無反応)〜+4(著明な興奮)までの11段階で鎮静レベルを評価します。
ABCDEFバンドルにおける推奨鎮静レベル:
▶ RASS:0(覚醒・落ち着いている)〜 −1(やや眠いが容易に覚醒)
この範囲が「浅い鎮静(light sedation)」とされ、
- 意思疎通が可能
- 呼吸状態やリハビリテーションへの参加が良好
- せん妄の予防にもつながる
という理由から推奨されています。
鎮痛・鎮静薬の選択ポイント
- 鎮痛薬:フェンタニル、モルヒネなど。腎・肝機能に応じて調整。
- 鎮静薬:
- 推奨:デクスメデトミジン(覚醒状態を保ちつつ穏やかな鎮静)
- 慎重に使用:プロポフォール(長期使用や高用量に注意)
- 回避推奨:ベンゾジアゼピン系(せん妄リスク増)
- 原則は“Analgesia First”:不穏や不安の原因が痛みにある場合は、まず鎮痛の最適化を優先
チームでの実践ポイント
- 看護師によるRASSでの評価を1日複数回実施し、多職種で共有
- リハビリテーション介入、人工呼吸器の離脱、せん妄予防など、全体の流れを見据えて調整
- 「C」の調整次第で、以降の「D(せん妄)」「E(離床)」にも影響を与える
理学療法士として鎮静をどう捉えるか
疼痛管理と同様に、理学療法士としては後述するE:Early Mobility and Exercise 早期離床と運動の促進において、鎮静のコントロールも重要となります。
重症患者リハビリテーション診療ガイドライン20236)では以下の鎮静コントロールが推奨されています。
- – 2 ≤ RASS ≤ + 1
- 安全管理のためのスタッフ配置が十分な場合、RASS + 2 も可
これらを目安に離床を実施する場合の鎮静コントロールを依頼することが重要です。
D:Delirium – Assess, Prevent, and Manage せん妄の評価・予防・管理
「D」は、ICUにおける**せん妄(Delirium)**への対応を明確にする項目です。
せん妄とは、急性に生じる意識・注意・認知の障害で、ICU患者の約3〜8割に発生すると言われています。
一見すると一時的な混乱に見えるかもしれませんが、せん妄を放置すると死亡率の上昇・長期的な認知障害のリスクが高まることが明らかになっており、ICUケアにおける最重要課題の一つとされています。
なぜせん妄への対応が必要なのか?
ICUにおけるせん妄の発症は、ICU在室期間の延長11)、人工呼吸器装着期間の延長11)、院内死亡率の増加12)、退院後のQOL低下・認知機能障害13)14)といった、多くの不利なアウトカムと強く関連しています。
特に、高齢者、深鎮静、感染症、睡眠障害、多剤併用などがリスク因子として指摘されています11)12)。
評価:毎日のスクリーニングが基本
せん妄は外見からだけでは判断できないため、客観的なスクリーニングツールを用いて評価します。
▶ CAM-ICU(Confusion Assessment Method for the ICU)
▶ ICDSC(Intensive Care Delirium Screening Checklist)
これらはRASSが−3以上(=呼びかけに反応するレベル)の患者に対して実施します。
予防:リスクを事前に減らす工夫
- 適切な鎮痛・鎮静(深鎮静を避ける)
- 睡眠環境の調整(昼夜のリズム、音・光のコントロール)
- メガネや補聴器などの使用を促し、感覚の遮断を防ぐ
- 会話や再定向(「今はICUにいますよ」「今日の予定は○○です」など)
管理:非薬物的アプローチが第一選択
- まずは原因の除去(感染、低酸素、薬剤など)
- 鎮静薬の見直し(ベンゾジアゼピン系はせん妄を悪化させる)
- 必要時に限り薬物治療(ハロペリドールやクエチアピンなど)を使用
- ただし薬物は最終手段。非薬物的ケアが基本
現場でのチーム連携ポイント
- 看護師・医師・リハビリテーションスタッフ・家族など、多職種で症状変化に気づくことが大切
- CAM-ICUの結果を日々共有し、状況に応じて対策を調整
- せん妄が落ち着くことで、リハビリテーションや離床がスムーズに進む
「D」は、「B(覚醒・呼吸)」「C(鎮静)」との関係が深く、バンドル全体のつながりの中でとても重要な位置づけです。
E:Early Mobility and Exercise 早期離床と運動の促進
「E」は、ICUにおける早期リハビリテーションの実施を明確に打ち出す項目です。
ICUでは、患者さんの状態が重篤なことからベッド上安静が続きがちですが、実はそれが廃用や筋力低下(ICU‑AW:ICU-acquired weakness)を引き起こす大きな要因になっています15)16)。
そこで、「E」では意識が戻ってからではなく、できるだけ早い段階から「動く」ことを支援することが推奨されています。
なぜ早期離床が重要なのか?
ICUでは、患者さんの状態が重篤なことからベッド上安静が続きがちですが、実はそれが廃用や筋力低下(ICU‑AW)を引き起こす大きな要因になっています17)。ICUでは1日安静にしているだけで筋力が2〜3%ずつ低下すると考えられており18)、ICU‑AWはADL・QOLの長期的な低下に直結しており19)、動かないことで肺炎・血栓・せん妄・褥瘡などの合併症リスクも高まります20)。
一方、早期から離床を行った群では、ICU滞在日数・人工呼吸器装着期間・せん妄発症率の低下が報告されています21)。
どのように進めるか?
- 重症患者リハビリテーション診療ガイドライン20236)の離床開始基準を参考にして離床を進める
- 座位保持 → 端座位 → 立位 → 歩行と段階的にステップアップ
- リハビリテーションスタッフ(理学療法士)が、医師・看護師と連携して可動域・筋力・バイタルサイン・動作能力などを確認しながら介入
安全に配慮した実施判断
- ICUでのリハビリテーションは「何もしないか、やりすぎるか」ではなく、適切なタイミングと量を判断することが重要
- 重症患者リハビリテーション診療ガイドライン20236)の開始基準、中止基準を参考にチームで検討すること
- 早期離床の可否を、毎朝のカンファレンスで確認する文化が鍵
医療チームでの連携のポイント
- 医師の離床許可だけでなく、看護師・リハビリテーションスタッフ・薬剤師が情報を共有し、適切な支援体制を整える(看護師によるルート類の整理や管理、薬剤師や看護師による鎮痛鎮静の適切なコントロール)
- 鎮痛・鎮静(A~C)が適切であることが、離床成功の前提条件
- 看護師によるポジショニングや座位保持の工夫も含めて「運動」と捉える視点が重要
この「E」は、筋力・機能回復だけでなく、患者の自立と退院後の生活に直結する要素です。
「D(せん妄)」との相互作用も大きく、離床によってせん妄の予防・改善効果も得られるとされています22)23)。
F:Family Engagement and Empowerment 家族の関与と支援の促進
「F」は、ABCDEFバンドルの中でも患者さんの心理的安定や回復後の生活に最も密接に関わる重要な視点です。
ICUという特殊で不安の多い環境において、家族が果たす役割は非常に大きく、積極的に関わってもらうことで、患者・家族双方の満足度や精神的健康を高める効果が期待されます24)25)。
なぜ「家族の関与」が重要なのか?
- ICU患者は意識障害やせん妄により、自分がどこにいるのか・何が起きているのか分からなくなる
- 家族がそばにいることで、安心感・再定向・せん妄予防につながる
- 家族自身も、**「ICUショック」や「PICS-F(家族版PICS)」**に苦しむことがある
- 家族の不安軽減・理解促進が、患者のケアへの参加意欲や退院後の支援力の強化に直結
具体的にどんな取り組みをするのか?
- 面会制限の緩和・柔軟な対応(可能な範囲でのオープンビジテーション)
- 家族へのわかりやすい説明・情報共有(診療内容、予後、今後の方針)
- ICU日記の導入(患者と家族が経過を振り返れるようにする取り組み)
- 家族が患者に話しかける・触れる・写真を見せるなどの情緒的関与の促進
Empowerment(力づけ)とは?
単に「参加させる」だけでなく、家族が自分の役割や立場に自信を持てるようサポートすることを意味します。
- 「患者のそばにいてあげること自体が治療の一部」だと伝える
- 退院後に必要となる介護・支援についても早期から情報提供
- 医療者との信頼関係を築き、安心して判断・協力できる環境づくり
チームでの実践ポイント
- 医師・看護師・MSW(医療ソーシャルワーカー)・リハビリテーションスタッフなど、それぞれの職種が家族との接点を持つ
- 回診やカンファレンス時に家族が同席できる仕組みを作る
- ICU全体で「家族もチームの一員」という意識を共有する
「F」は、患者さんの“医療”という枠を超えた人としての尊厳や絆を大切にする項目です。
ABCDEFバンドルの中でも、「文化の変革」が必要とされる部分であり、ICUケアの人間性・倫理性が問われる要素でもあります。
ABCDEF”GH”バンドルとしても提唱されている
従来のABCDEFバンドルに加えて「G」と「H」を組み入れた“ABCDEFGHバンドル”が提案されており、Post‑Intensive Care Syndrome(PICS)およびPICS-Fへの対応を視野に入れた包括的ケアモデルとして注目されています26)。これはPICS(Post Intensive Care Syndrome:集中治療後症候群)の予防を目的とした提案型の包括的介入セットとして記述されており、多職種による日々のICUケアと継続的なフォローを組み合わせたアプローチです。
「G」と「H」の項目概要
ナラティブレビューにより提示されている「ABCDEFGHバンドル」において、GとHはPICS予防・家族支援の強化に焦点を当てた追加項目として位置づけられています 。
G:Good communication practices with the family members from the medical team to prevent PICS‑F
- 医療チームによる家族との良好なコミュニケーションの実践。
- ICUにおける情報共有や説明の質を高めることで、PICS-F(患者の家族に生じる心理的障害)を未然に防ぐことを狙いとしています。
H:Hand‑out material provided to families to allow a better understanding of the ICU environment
- ICU環境やケア内容について家族向けの資料を提供する取り組み。
- 家族がICUの雰囲気、治療プロセス、予後情報などを理解しやすくすることで、不安軽減や支援者としてのエンパワーメントにつなげるものです。
ナラティブレビューとは、特定のテーマに関する既存の研究を物語のように記述し、背景や文脈を理解するためのレビューのことです。システマティックレビューとは異なり、厳密な方法論に基づいたものではなく、研究者の解釈や視点が含まれることがあります。したがって、ナラティブレビューは全体像を把握するうえで有用ですが、エビデンスの質としては必ずしも高くない点には留意が必要です。
ナラティブレビューの特徴:
- 物語のような記述:特定のテーマに関する研究を、ストーリーを語るようにまとめる。
- 背景や文脈の理解:研究の背景や文脈を理解するのに役立つ。
- 研究者の解釈:研究者の視点や解釈が含まれることがある。
- 厳密な方法論の欠如:システマティックレビューのような厳密な方法論に基づかない。
- 幅広い疑問やテーマ:滅多に報告されない疑問や一般的疑問も扱うことがある。
- 質的分析が中心:結果の質的分析が中心で、データの再現性は低い場合がある。
ナラティブレビューの目的:
- 特定の分野の現状を把握する。
- 研究の背景や文脈を理解する。
- 新たな研究テーマや視点を見つける。
- 既存の研究を批判的に考察する。
ナラティブレビューとシステマティックレビューの違い:
| 特徴 | ナラティブレビュー | システマティックレビュー |
|---|---|---|
| 方法論 | 厳密な方法論に基づかない | 厳密な方法論に基づき、再現性がある |
| 記述 | 物語のように記述 | 客観的なデータに基づいて記述 |
| 解釈 | 研究者の解釈や視点が含まれる | 客観的なデータに基づいて分析・評価 |
| 目的 | 背景や文脈の理解、新たな視点の提示 | エビデンスの統合、結論の導出 |
| 参考文献数 | 少ない場合もあれば、多い場合もある | 網羅的に収集・評価するため、多い傾向がある |
まとめ|ABCDEFバンドルは“共通言語”であり、回復への道しるべ
ABCDEFバンドルは、ICUにおける重症患者ケアを多職種が共通の視点で支えるためのフレームワークです。
一つひとつの項目には、患者さんの命だけでなく、その後の生活やQOLを守るための意味と根拠が詰まっています。
🔹 A~Fのポイントを振り返ると…
| 項目 | 内容 | 目的 |
| A | 痛みの評価・予防・管理 | ストレス軽減・回復促進 |
| B | 自発覚醒・自発呼吸トライアル | 人工呼吸器離脱・せん妄予防 |
| C | 鎮痛・鎮静薬の適切な選択 | 過鎮静を避け、せん妄を防ぐ |
| D | せん妄の評価・予防・管理 | 精神的後遺症の予防・早期対応 |
| E | 早期離床と運動 | ICU-AW予防・自立支援 |
| F | 家族の関与と支援 | 安心感の提供・PICS-F予防 |
このバンドルは単なるチェックリストではなく、「今日のこの患者さんに、何が必要か?」を考える土台として現場で活かせるものです。
また、近年では**「G(Good communication)」「H(Handout資料の活用)」を加えたABCDEFGHバンドル**として、PICS・PICS-Fの予防を視野に入れた包括的ケアの提案も始まっています。
💬 現場で大切なのは、「毎日やる」こと
ABCDEFバンドルは、難しいことを新たに始めるのではなく、すでに行っている日々のケアを「見える化」し、質をそろえるためのツールです。
ICUの文化として、毎日の回診やカンファレンスでA〜Fを一つひとつ確認する習慣が根づけば、患者さんの未来も、医療者の連携も、確実に変わっていきます。
引用文献
1)Marra A, Ely EW, Pandharipande PP, et al. The ABCDEF bundle in critical care. Critical Care Clinics. 2017 Oct;33(4):225–243. doi:10.1016/j.ccc.2017.03.014
2)Balas MC, Vasilevskis EE, Burke WJ, et al. Critical care nurses’ role in implementing the “ABCDE Bundle” into practice. Critical Care Nurse. 2014 Aug;34(4):44-64. doi:10.4037/ccn2014229
3)Morandi A, Brummel NE, Ely EW. Sedation, delirium and mechanical ventilation: the ABCDEF approach. Critical Care Clinics. 2013 Oct;29(4):663–680. doi:10.1016/j.ccc.2013.06.005
4)Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults. Critical Care Medicine. 2021 Jul;49(7):109-120. doi:10.1097/CCM.0000000000005029
5)Pun BT, Balas MC, Barnes‑Daly MA, et al.Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults.Crit Care Med. 2019 Jan;47(1):3–14. doi:10.1097/CCM.0000000000003482
6)Unoki T, Hayashida K, Kawai Y, et al.Japanese Clinical Practice Guidelines for Rehabilitation in Critically Ill Patients 2023 (J‑ReCIP 2023).Journal of Intensive Care. 2023;11(1):47.
doi:10.1186/s40560-023-00697-w
7)Gitti N, Renzi S, Marchesi M, et al.Seeking the Light in Intensive Care Unit Sedation: The Optimal Sedation Strategy for Critically Ill Patients.Front Med (Lausanne). 2022;9:901343.doi:10.3389/fmed.2022.901343
8)Hermans G, Van den Berghe G, Latronico N, et al.Intensive care unit-acquired weakness: impact on ICU stay, weaning, and mortality.Front Med (Lausanne).2022;9:792201.doi:10.3389/fmed.2022.792201
9)Li Y, Yuan Y, Ma L.Sedation depth is associated with increased mechanical ventilation duration, delirium, and increased hospital length-of-stay.Critical Care. 2020;24:162.
doi:10.1186/s13054-020-02928-1
10)Gitti N, Renzi S, Marchesi M, et al.Seeking the Light in Intensive Care Unit Sedation: The Optimal Sedation Strategy for Critically Ill Patients.Front Med (Lausanne). 2022;9:901343.
doi:10.3389/fmed.2022.901343
11)Ely EW, Shintani A, Truman B, et al.Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit.JAMA. 2004;291(14):1753–1762.
doi:10.1001/jama.291.14.1753
12)de Rooij SE, Schuurmans MJ, van der Mast RC, Levi M.Predisposing and precipitating factors associated with delirium: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2005;20(7):609–615.
doi:10.1002/gps.1330
13)Hopkins RO, Jackson JC.Long-term cognitive and psychological outcomes after critical illness. Clin Chest Med. 2009;30(3): 591–600.
doi:10.1016/j.ccm.2009.05.008
14)Girard TD, Pandharipande PP, Hughes CG, et al.Delirium as a predictor of long-term cognitive impairment after critical illness. Crit Care Med. 2010;38(7):1513–1520.
doi:10.1097/CCM.0b013e3181eee12b
15)Hermans G, Van den Berghe G.Clinical review: intensive care unit acquired weakness.
Crit Care. 2015;19(1):274.
doi:10.1186/s13054-015-0993-7
16)Chen J, Huang M.Intensive care unit-acquired weakness: Recent insights.
One recent review article; PMC‑NCBI. 2024.
17)Hermans G, Van den Berghe G.Clinical review: intensive care unit acquired weakness.Critical Care. 2015;19:274.
doi:10.1186/s13054-015-0993-7
18)Haines KJ, Skinner EH, Berney S, et al.Early mobilisation in the intensive care unit: a combined perspective.Crit Care Resusc. 2013;15(3):186–191.
19)Wieske L, Verhamme C, Nollet F, et al.Impact of ICU-acquired weakness on post-ICU physical functioning: A follow-up study.Critical Care. 2015;19:196.
doi:10.1186/s13054-015-0993-7
20)Hermans G, Latronico N.Clinical review: Early patient mobilization in the ICU.Critical Care. 2013;17:207.
doi:10.1186/cc11820
21)The ANZICS Clinical Trials Group (TEAM) Investigators.Early active mobilization during mechanical ventilation in the ICU.New England Journal of Medicine. 2022;387:1747–1758. doi:10.1056/NEJMoa2209083
22)Zhou L, Zeng Y, Wang R, Cai Y, Xu F, Chen B. Preventive effects of early mobilisation on delirium incidence in critically ill patients: systematic review and meta‑analysis. Med Klin Intensivmed Notfmed. 2025;120:??–??. doi:10.1007/s00063-024-01243-8
23)Zhang L, Hu W, Cai Z, Liu J, Wu J, Deng Y, et al. Early mobilization of critically ill patients in the intensive care unit: a systematic review and meta‑analysis. PLoS ONE. 2019;14(10):e0223185. doi:10.1371/journal.pone.0223185
24)Davidson JE, Powers KE, Hedayat KM, et al.Patient and family engagement in the ICU: untapped opportunities. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(9):120–129. doi:10.1164/rccm.201710-2032CI
25)Engelman DT, Miocic J, Greenland JR, et al.Family engagement in the adult cardiac intensive care unit is associated with improved medical goal achievement, patient and family experience, satisfaction with care, and delirium prevention. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2025;? (online ahead of print). doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010084
26)Benedetti G, Santini S, Monzani D, et al.Post‑Intensive Care Syndrome as a Burden for Patients and Their Caregivers: A Narrative Review.Journal of Clinical Medicine. 2024;13(19):5881. doi:10.3390/jcm13195881