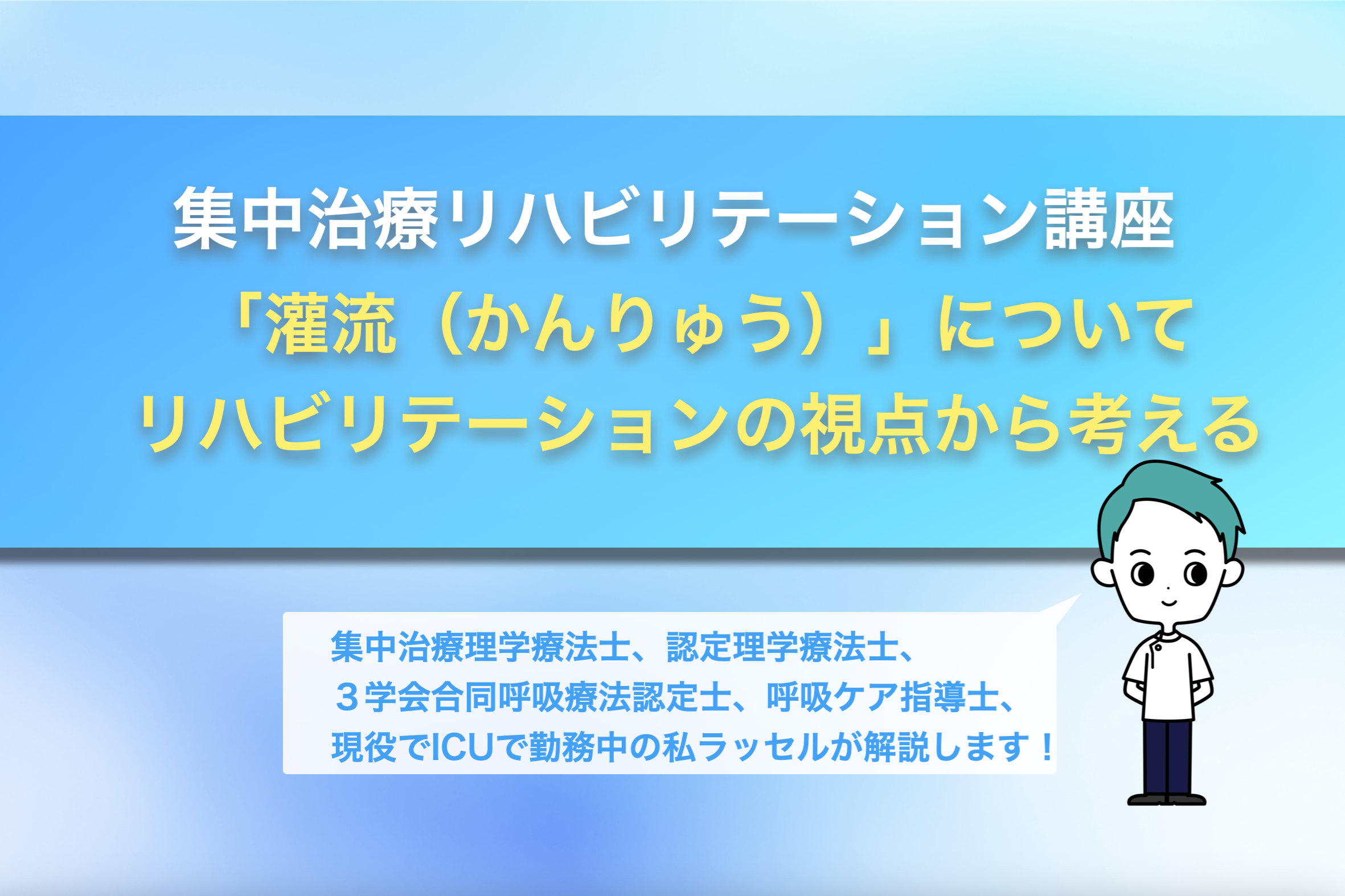そもそも「灌流」とは何か?
「灌流(かんりゅう)」とは、酸素や栄養を含んだ血液が、心臓から全身の組織・臓器に向かって運ばれ、細胞レベルにまで届くプロセスのことを指します。英語では “perfusion” と呼ばれ、集中治療の現場では極めて重要な概念のひとつです。
灌流が適切に保たれているかどうかは、生命維持の基本であり、あらゆる治療やリハビリテーション介入の“前提条件”となります。なぜなら、どれだけ呼吸状態が安定していても、どれだけ血圧や心拍が正常に見えても、最終的に“酸素が細胞に届いていなければ”意味がないからです。
特にICUに入室するような重症患者では、灌流が部分的または全身的に低下している可能性が常にあります。その状態で過度な運動を行えば、心臓や脳、腎臓などの臓器にさらなるダメージを与えるリスクがあるため、リハビリテーションの可否判断において灌流の評価は欠かせません。
また、灌流という言葉はしばしば「循環」と混同されがちですが、実際にはもう少し複雑な意味を持ちます。循環が「血液を送る機能」とすれば、灌流は「送られた血液が必要な場所に適切に届き、役割を果たしているかどうか」という質の評価に近いものです。
この「灌流」のメカニズムには、
- 肺での酸素取り込み(呼吸)
- 心臓からの血液の拍出(循環)
- 赤血球・ヘモグロビンによる酸素運搬(血液)
といった複数の要素が関係しています。
次にこれらの3つの柱を中心に、灌流を維持するために必要な条件を一つずつ紐解いていきます。
灌流を支える3本柱:呼吸・循環・貧血
灌流が成り立つためには、単に血液が流れていればよいというわけではありません。
重要なのは、「その血液に酸素が含まれており、それが十分に組織に届けられているかどうか」です。これを支えているのが、次の3つの生理機能です。
① 呼吸(酸素を取り込む力)
肺は、外界から酸素を取り込み、それを血液中のヘモグロビンに結びつける役割を担っています。
この過程に問題があると、血液の中に酸素がそもそも取り込まれないため、いくら循環が回っていても、酸素の“中身”が足りない状態になります。
ARDS(急性呼吸窮迫症候群)やCOVID-19肺炎などの疾患では、まさにこの呼吸機能の破綻が灌流のボトルネックになります。
② 循環(酸素を送る力)
心臓がしっかりと収縮して血液を全身に送り出すこと、つまり血液を運ぶポンプ機能が正常であることも灌流には欠かせません。
たとえば心原性ショックや循環不全の状態では、肺で取り込んだ酸素があっても、それを必要な組織に送り届ける力が不足しています。
また、心拍出量だけでなく、血圧や血管の収縮状態なども含めて、「血液を押し出す機能」全体が問われます。
③ 血液(酸素を運ぶ力)
呼吸で取り込まれた酸素は、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビン(Hb)に乗って運ばれます。
血液中の酸素の約98〜99%はヘモグロビンと結合して運搬されており、溶け込んでいる酸素はごくわずか(1〜2%未満)です1)2)。このため、酸素運搬能を評価する際は、Hb濃度やSaO₂が最重要であり、PaO₂の変化だけでは輸送量に大きな影響は与えません2)。
貧血や出血によってヘモグロビンが不足していると、心拍出量が正常でも酸素を運ぶ“トラック”そのものが不足している状態になります。
ICUでは、急性期出血後や慢性疾患による貧血、希釈性の影響など、さまざまな理由で酸素運搬能が低下していることがあります。
この点もリハビリテーション可否の判断材料として見逃せません。
「どれか1つ」でも欠ければ、灌流障害は起きる
この3本柱は、互いに連携しながら全身への酸素供給を支えています。
つまり、どれか1つでも機能が破綻すれば、たとえ他が正常でも組織への酸素供給は不足してしまいます。
例えば、
- 肺炎で酸素化が悪ければ → 血中酸素が足りない
- 心不全で心拍出量が低ければ → 血液が届かない
- 貧血でHbが低ければ → 酸素を運べない
このように、灌流はシステム全体としての機能評価が必要なのです。
次はこの“供給の構造”だけでなく、「どれだけ酸素が必要とされているか(需要)」とのバランスという新しい視点を紹介していきます。
もう一つのキーワード:酸素需要と供給のバランス
灌流(perfusion)を語るうえで、もう一つ忘れてはいけない視点があります。
それは、「どれだけ酸素を供給できるか(DO₂)」だけでなく、「どれだけ酸素を必要としているか(VO₂)」とのバランスを見ることです。
たとえ血圧や心拍数、SpO₂といった指標が安定していても、細胞レベルで酸素が足りていなければ、灌流は十分とは言えません。
このギャップを見抜けるかどうかが、ICUでのリハビリテーションの判断において非常に重要になります。
ICU患者では“酸素需要”が高まりやすい
ICUに入室している患者さんは、感染、発熱、せん妄、疼痛、不穏などのストレスによって、通常よりも酸素消費量が増加していることがよくあります。
また、人工呼吸器の設定や酸素化が保たれていても、実際には酸素を“使う側”の需要が上回っていることも少なくありません。
このような状態で、灌流の“見た目”だけを信じて過剰に離床してしまうと、組織や臓器が酸素不足に陥り、悪化を招く可能性があります。
DO₂・VO₂・O₂ERの関係
酸素供給量(DO₂)と酸素消費量(VO₂)の関係を評価することで、細胞がどれだけ“酸素を欲しがっているか”をある程度把握できます。
DO₂・VO₂・O₂ERとは?
酸素の「運搬」「消費」「利用効率」を表す三つの基本指標です。
臨床での酸素需給バランスの評価やショック状態の判断に重要です。
灌流を理解するための基本指標と略語の整理
酸素は、呼吸・循環・血液によって全身へ運ばれ、各組織で消費されます。
この過程を定量的に理解するために用いられるのが以下の指標です。
ここでは略語の意味、定義、計算式、臨床での位置づけを一括で整理します。
1.DO₂(酸素供給量/Oxygen Delivery)
- 略の意味:Delivery of Oxygen
- 定義:単位時間あたりに全身の組織へ供給される酸素の総量
- 単位:mL/min
- 計算式:
DO₂ = 心拍出量(CO) × 動脈血酸素含有量(CaO₂) × 10
※「×10」は dL → L 換算 - CaO₂の計算式:
CaO₂ = 1.34 × Hb × SaO₂ + 0.0031 × PaO₂ - 臨床での位置づけ:
酸素供給側の中心的指標。COやHb、SaO₂の影響を強く受け、DO₂が低下すると灌流不全のリスクが高まる。
2.VO₂(酸素消費量/Oxygen Consumption)
- 略の意味:Volume of Oxygen consumed
- 定義:単位時間あたりに組織で実際に消費された酸素の総量
- 単位:mL/min
- 計算式:
VO₂ = 心拍出量(CO) ×(CaO₂ − CvO₂)× 10 - 臨床での位置づけ:
酸素需要側の指標。発熱、感染、疼痛、不穏、運動などで増加する。代謝亢進状態ではVO₂が上昇。
3.O₂ER(酸素抽出率/Oxygen Extraction Ratio)
- 略の意味:Oxygen Extraction Ratio
- 定義:DO₂(供給された酸素)のうち、VO₂として実際に消費された割合
- 単位:%
- 正常値:25~30%
- 計算式:
O₂ER = VO₂ ÷ DO₂ × 100
=(CaO₂ − CvO₂)÷ CaO₂ × 100 - 臨床での位置づけ:
組織がどれだけ酸素を効率的に利用しているかを表す。
O₂ERが高い → 組織が酸素を限界まで使っている(灌流の余裕が少ない)
O₂ERが低い → 酸素供給に対して需要が少ない/またはミトコンドリア障害などで使えていない
4.CO(心拍出量/Cardiac Output)
- 略の意味:Cardiac Output
- 定義:心臓が1分間に全身へ送り出す血液量
- 単位:L/min
- 臨床での位置づけ:
DO₂を決定する主要因の一つ。低COでは酸素供給量が減り、組織灌流が不足する。
5.CaO₂(動脈血酸素含有量/Arterial Oxygen Content)
- 略の意味:Content of Arterial Oxygen
- 定義:動脈血1dLあたりに含まれる酸素の量
- 単位:mL O₂/dL
- 計算式:
CaO₂ = 1.34 × Hb × SaO₂ + 0.0031 × PaO₂
(※1.34は1gのHbが結合できるO₂量/0.0031は溶解酸素の係数) - 臨床での位置づけ:
Hb・SaO₂の影響を強く受ける。DO₂の“質”を左右する重要因子。
6.PaO₂(動脈血酸素分圧/Partial Pressure of Arterial Oxygen)
- 略の意味:Partial Pressure of Arterial Oxygen
- 定義:動脈血中に溶け込んでいる酸素の圧(mmHg)
- 臨床での位置づけ:
酸素化の評価に用いられる。DO₂に与える影響は小さいが、呼吸機能の評価には重要。
Hbに結合していない“溶解酸素”を反映する。
動脈(CaO₂)
↓(DO₂:酸素が届けられる)
組織で消費(VO₂)
↓
静脈(CvO₂)
↓
O₂ER:届けられたうち、どれだけ使われたか
- DO₂が高いほど、酸素はたくさん供給される
- VO₂が多いほど、組織は酸素を活発に消費している
- O₂ERが高い=ギリギリまで酸素を使っている状態(灌流余裕がない)
- O₂ERが低い=灌流に余裕がある or 酸素利用障害がある
灌流が追いつかないとどうなるか?
もし酸素供給が需要に追いつかなくなると、細胞は嫌気性代謝へと移行し、エネルギー効率の悪い“酸素なしの代謝”が始まります。教科書などで見る好気性回路(ミトコンドリアでのクエン酸回路)から、解糖系(嫌気的解糖)への移行です。
このとき生じるのが乳酸(lactate)であり、血中乳酸濃度の上昇は灌流不全の代表的サインとして広く使われています。
つまり、高乳酸=細胞レベルで酸素が足りていない可能性ということです。
リハビリテーションの前に、“酸素の余裕”を考える
灌流の可否を考えるときは、単に「供給があるか?」だけでなく、
- その供給で足りているか?
- 需要が上がっていないか?
- 組織がギリギリの状態ではないか?
といった、バランスと余裕度を評価する視点が欠かせません。
とくに重症患者においては、「一見安定して見える状態」に隠れた需要の増大を見逃さないことが、安全なリハビリテーションの鍵になります。
見落とされがちな要素:微小循環と血管トーン(トーヌス)
灌流を評価する際、つい心拍出量や血圧など大きな循環指標(マクロ循環)ばかりに目が向きがちですが、
実際に酸素が末梢の細胞に届いているかどうかを決定づけるのは、**毛細血管レベルの「微小循環」**や、**血管の緊張状態である「血管トーン(トーヌス)」**です。
この“見えにくい灌流”の部分まで意識することで、より安全で適切なリハビリテーション判断が可能になります。
微小循環:本当に末梢に酸素が届いているか?
心臓から送り出された血液が動脈を通り、最終的にたどり着くのが毛細血管レベルの微小循環です。
この微小循環が破綻していると、血圧や心拍が正常でも組織への酸素供給が不十分になります。
たとえば敗血症では、
- 血管内皮の障害
- 血液の粘稠度変化
- 局所の流れの不均一化
などが原因で、血液が必要な部位に届かない“シャント様”の状態が生じることがあります。
このような状態では、見かけ上の循環が安定していても、実質的な灌流は破綻している可能性があるのです。
血管トーン(トーヌス):血管が調整できているか?
血管トーン(トーヌス)とは、血管の平滑筋の緊張状態を指し、血管が状況に応じて収縮・拡張する能力のことです。
通常は自律神経やホルモンによってこのトーヌスが調整され、臓器ごとの血流配分が最適化されています。
しかし、敗血症性ショックや炎症性疾患などでは、
- 血管が拡張したままになってしまう(トーヌス低下)
- 末梢の血管が強く収縮してしまう(過剰なトーヌス亢進)
といった異常が起こり、灌流のコントロールが破綻します。
たとえば皮膚や腎臓などの“非優先臓器”では、血流が著しく低下し、低灌流状態にもかかわらず血圧は保たれているという現象が起こることがあります。
現場での評価:観察が重要なヒントになる
微小循環や血管トーン(トーヌス)は、心拍出量のように直接数値でモニタリングできるものではありません。
そのため、ベッドサイドでの臨床観察が非常に重要になります。
代表的な評価項目は以下の通りです:
- 毛細血管再充満時間(CRT):2秒以上の遅延は微小循環障害の兆候
- 末梢冷感や皮膚温度の左右差
- 皮膚の色調変化(チアノーゼや斑状)
- 尿量の低下や意識レベルの変化
これらの情報を総合して、「見た目のバイタルが正常でも、組織への灌流は不十分かもしれない」というリスクを見抜くことが大切です。
灌流の“質”を見極めて、安全なリハビリテーション判断へ
灌流の評価には、「どれだけ血液を送れているか」だけでなく、
「それが本当に末梢まで届いているか」、そして「血管が適切に反応しているか」という質的な視点が欠かせません。
このような“見えにくい灌流”まで意識することが、重症患者に対する安全なリハビリテーション介入の第一歩となります。
こうした灌流の良否をどのように現場で判断するか、具体的な指標と評価方法を紹介していきます。
灌流が足りているかをどう判断するか?
リハビリテーションの介入において、患者の灌流状態が「今、安全と言えるかどうか」を見極めることは非常に重要です。
しかし灌流は、心拍数や血圧といった単一の数値だけでは評価できません。
複数の観察所見や指標を総合的に捉えることで、灌流の良否を判断する必要があります。
灌流不全の兆候は“臓器ごとのサイン”として現れる
灌流が不十分になると、まず影響を受けやすいのは、酸素需要の高い臓器や末梢循環の弱い部分です。
それぞれの臓器が“灌流不足を訴えるサイン”を発してくれることが多く、これをベッドサイドで丁寧に拾うことが重要です。
代表的な灌流評価の観察ポイント
以下は、灌流不全を示唆する臨床的な兆候・指標です:
- 毛細血管再充満時間(CRT):指先や膝下の皮膚を圧迫し、色が戻るまでの時間。2秒以上で遅延と判断。
- 四肢末梢の冷感:手足の冷たさや皮膚の湿潤は、末梢灌流の低下を反映している可能性があります。
- 皮膚色調の変化:チアノーゼ、斑状、還流の悪さなどが目視で確認される。
- 尿量の減少:腎臓は灌流低下に敏感な臓器。0.5 mL/kg/hを下回ると注意が必要。
- 意識レベルの変化:脳の灌流が低下すると、傾眠傾向や注意障害、不穏などが出現しやすくなります。
- 乳酸値の上昇:嫌気性代謝の進行により産生される乳酸は、全身の灌流不全を示す間接的なマーカーです。
- 中心静脈酸素飽和度(ScvO₂)や混合静脈血酸素飽和度(SvO₂):侵襲的評価となりますが、酸素の“使われ具合”を把握する指標です。
“数値”よりも“変化”を見る意識が大切
灌流の指標は、単発の絶対値だけでなく、時間経過や介入前後の変化を追うことが重要です。
たとえば尿量が1時間前より減ってきている、CRTが少しずつ延びてきている、といった微細な変化は、早期に灌流不全を示唆するサインになり得ます。
また、「患者の顔色が悪くなってきた」「ぼーっとしてきた」など、定量化しにくい変化にも敏感になることが、現場では非常に役立ちます。
灌流状態を意識したリハビリテーションの判断へ
リハビリテーションの実施判断においては、全身状態のバイタルだけでなく、
“酸素がきちんと細胞に届いているか”という灌流の視点を持つこと
“今は安全か”を総合的に読み解く観察力を持つこと
が何より重要です。
たとえ血圧やSpO₂が安定していても、臓器が灌流不全のサインを出しているなら、介入は控えるべきですし、逆にやや低めの血圧でも全身の還流が安定していれば、安全にリハビリテーションを進められるケースもあります。
灌流を“見抜く力”が介入の質を高める
灌流は、見た目の数値や単一の指標では測りきれません。
複数の所見を組み合わせて、身体が発している灌流不全のサインを見逃さないこと。
それが、安全で有効なリハビリテーションにつながっていきます。
まとめ:灌流とは“組織に届くかどうか”を見極めること
灌流とは、単に「血液が流れているかどうか」ではなく、
酸素や栄養を含んだ血液が、組織や細胞にきちんと“届いているかどうか”を評価する考え方です。
この視点を持つことで、リハビリテーション介入のリスクを減らし、
患者にとって安全かつ効果的なアプローチを選択することができます。
灌流を構成する複数の要素
灌流は、ひとつの数値や所見だけでは評価できません。
以下のような複数の側面を横断的にとらえることで、全体像を把握できます。
- 呼吸・循環・貧血という「酸素供給の3本柱」
- 酸素需要とのバランス(DO₂/VO₂)
- 微小循環と血管トーヌス(血管の調整機能)
- 臓器からの灌流不全サイン(尿量、意識、末梢冷感 など)
これらは互いに影響し合い、どれかひとつが破綻しても灌流障害が起き得ます。
「見えている数値が正常でも、本当に酸素が届いているとは限らない」
という前提で評価を進めることが重要です。
リハビリテーションの判断基準に“灌流”を据える意義
ICUでのリハビリテーション介入においては、
「心拍数や血圧が安定しているからOK」ではなく、
「今この瞬間、組織レベルで酸素が行き届いているか?」という問いを立てることが、
より本質的で安全な判断につながります。
灌流という視点を持てば、リスク回避だけでなく、
介入タイミングの最適化やアウトカムの向上にもつながるはずです。
引用文献
1)West JB. Pulmonary Pathophysiology: The Essentials. 9th ed. Wolters Kluwer; 2012.
2)Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 13th ed. Elsevier; 2015.