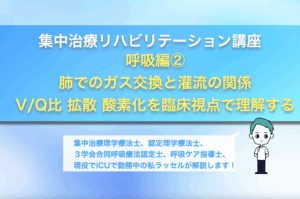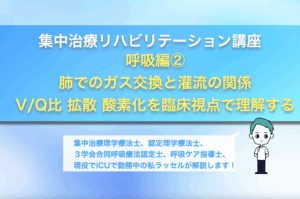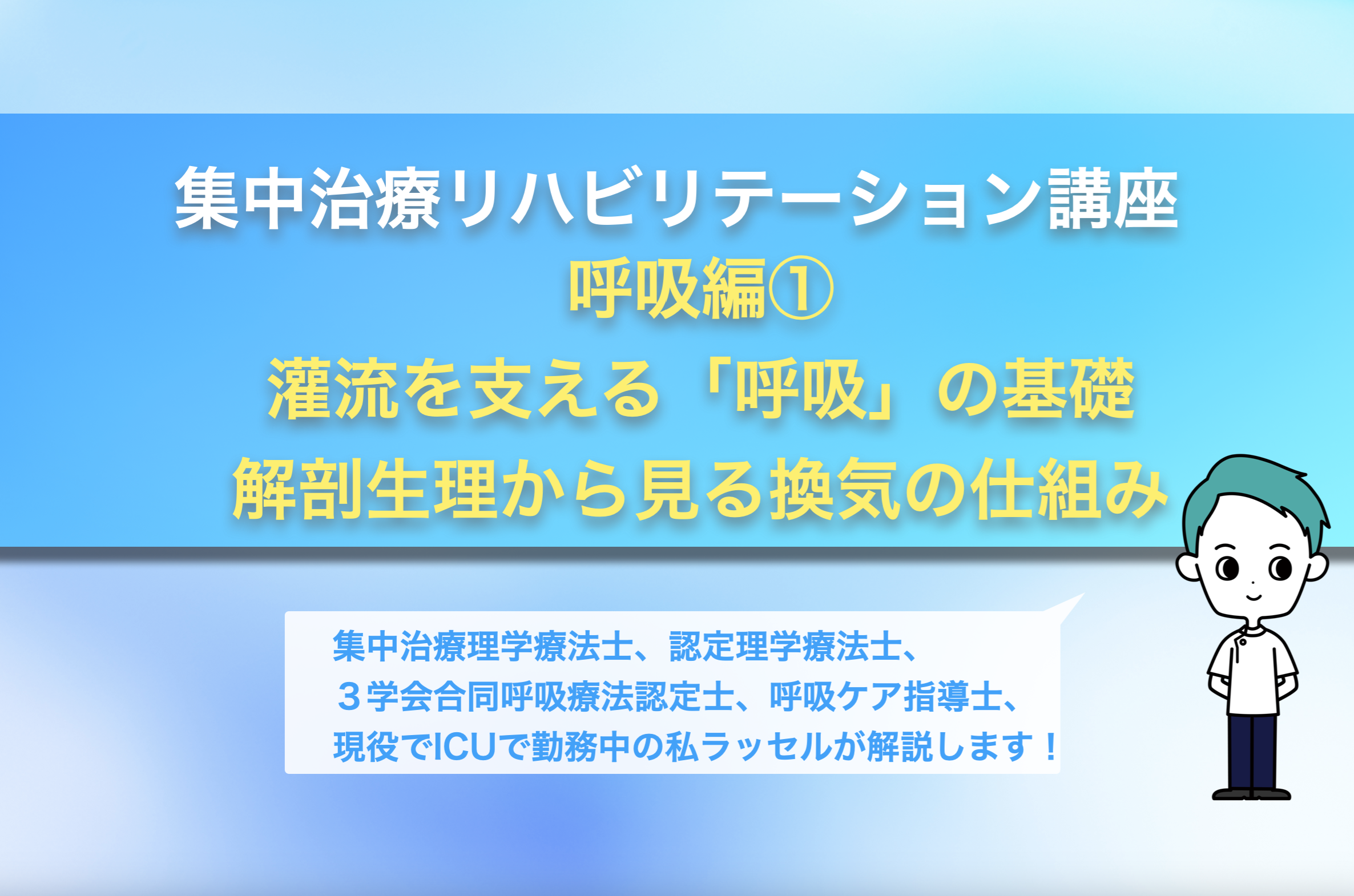なぜ“呼吸”の理解が灌流に重要なのか
酸素は、細胞のエネルギー代謝に欠かせない「生命の燃料」、車で言うとガソリンのようなものです。
ガソリンがないと車が動かないように、細胞も酸素がないとエネルギーを作り出せません。
その酸素を体内に取り込む最初のステップが、呼吸です。
つまり、呼吸は「灌流(Perfusion)」の入り口であり、灌流を支える土台です。
どれだけ血液が流れていても、呼吸によって酸素が肺から取り込まれていなければ、“酸素を含まない血液”が全身を巡るだけになります。
ガソリンの入っていない車で物資を配送しようとするようなもの。
すなわち、「呼吸が正常に機能していること」が灌流機能に直結するといえるのです。
臨床では、SpO₂をはじめとした酸素化の指標を見ることがありますが、これらはあくまで「呼吸と血液がうまくつながっているか」を見るための指標です。
このつながりを正しく理解するには、呼吸がどう成り立っているか(構造と機能)を知ることが前提になります。
また、呼吸障害は灌流に直接悪影響を及ぼします。
例えば、肺炎やARDSでは肺胞のガス交換が障害され、拡散がうまくいかず、動脈血酸素分圧(PaO₂)が低下します。
この状態では、心拍出量が正常でも、細胞に届く酸素は不足し、“呼吸が原因による灌流の障害”が生じるのです。
理学療法士を含む医療者にとって、呼吸の観察は灌流の評価そのものでもあります。
呼吸数、呼吸様式、呼吸筋の動員状況などから、身体が今どれだけ酸素を求めているか、どのように補おうとしているかが見えてきます。
本記事では、まず「呼吸とはどのような構造で成り立っているか」「どうやって酸素を肺に送り届けているのか」といった、呼吸の基本を構造と力学から整理していきます。
それがわかると、臨床での観察眼が一段と鋭くなり、灌流の異常にもいち早く気づけるようになります。
呼吸器の解剖|酸素の通り道とその役割
呼吸器は、外界の空気から酸素を取り込み、体内へ届ける“酸素の通り道”です。
その経路を理解することは、どこで障害が起きているかを見抜く基盤になります。
ここでは、呼吸に関わる主な解剖構造を「気道」「肺」「胸郭」の3つに分けて整理します。
気道の構造と役割(鼻腔〜肺胞入口まで)
外気が体内に入る最初のルートが「気道」です。
大きくは上気道(鼻腔〜咽頭)と下気道(喉頭〜肺胞入口)に分かれます。
- 鼻腔・咽頭・喉頭:空気の加温・加湿・異物除去を行うフィルター機能を持ちます。
- 気管:約10~12cmの軟骨性チューブで、空気を左右の肺に送ります。
- 気管支:気管から分岐し、左右の肺へと空気を届けます。さらに細かく枝分かれして細気管支へ。
- 終末細気管支〜呼吸細気管支〜肺胞:ガス交換の直前段階。呼吸細気管支にはごく少量のガス交換能力があります。
気道のどこかで狭窄や炎症が起こると、換気そのものが障害されます。
閉塞性疾患(COPD、喘息など)はこの「空気の通り道」に問題がある典型例です。
肺と肺胞|ガス交換の舞台
空気が最終的に届くのが「肺胞」です。
肺は左右に分かれ、**右肺は3葉(上葉・中葉・下葉)、左肺は2葉(上葉・下葉)**の構造をしています。
肺の中には約3〜5億個の肺胞があり、ここが酸素と二酸化炭素の交換を行う場です。
肺胞の壁は非常に薄く、その内側を毛細血管が取り囲んでいます。
この構造があるからこそ、拡散という自然な物理現象でガス交換が可能になります。
この肺胞構造が破壊されると、酸素取り込みの効率が大きく低下します。
たとえば、肺炎や肺線維症などでは、肺胞の壁が厚くなったり、液体が貯留したりして、ガス交換に支障を来たします。
胸郭|肺を動かす“呼吸の外殻”
肺そのものには筋肉がなく、自力で動くことはできません。
肺を拡張・収縮させているのが「胸郭」の動きです。
胸郭は、肋骨・胸骨・胸椎で構成され、内側に肺を包み込む構造になっています。
この胸郭の容積が広がることで、肺が引き伸ばされて陰圧が生まれ、空気が流れ込むのです(陰圧呼吸)。
また、胸郭の動きにはリズムがあります。
肋骨の上下動(ポンプハンドル)や外側の広がり(バケットハンドル)は、呼吸パターンの観察時に重要な指標になります。
上部肋骨はポンプハンドルモーション、下部肋骨はバケットハンドルモーションの原理にて肋骨は動いていますね!のちに詳しく解説します。
肋骨骨折や強直性脊椎炎などで胸郭が動かなくなると、肺の拡張が制限される=換気量が低下するという事態になります。
このように、「酸素が通る道筋」としての解剖構造を理解することは、呼吸障害の評価や介入において欠かせない知識です。
ここでは文章にて要点を列挙しました。
次章では、この構造を動かすための呼吸筋について掘り下げていきます。
呼吸を担う筋肉|自動性と随意性のはざまで
呼吸は、通常は意識しなくても自然に行われている生理現象です。
しかし、運動時や呼吸困難時には、意識的に息を深く吸ったり吐いたりすることもあります。
このように、呼吸は「自動性」と「随意性」の両面を持つ運動です。
その動きを生み出しているのが、呼吸筋と呼ばれる筋群です。
呼吸筋は、吸気時に胸郭を広げ、肺を拡張させるために働きます。
ここでは、主要な呼吸筋と補助呼吸筋の役割・臨床的意義について整理していきます。
主要呼吸筋:呼吸のベースを支える筋肉
安静呼吸の時に働く呼吸筋は2つです。
1つ目の主役は、横隔膜(diaphragm)です。
横隔膜は、胸腔と腹腔を隔てるドーム状の筋肉で、安静時の吸気において最も重要な筋です。
収縮すると下方に引き下がり、胸腔を陰圧にして肺を拡張させます。
2つ目は、外肋間筋(external intercostals)です。
肋骨の間を斜めに走行し、肋骨を持ち上げることで胸郭を広げます。
これも吸気に働く筋で、安静呼吸では横隔膜とともに作用します。
これらの筋が十分に活動できない状態(神経筋疾患、疲労など)では、安静時でも換気が困難になります。
補助呼吸筋:努力呼吸時に動員される筋群
運動時や呼吸困難時には、補助呼吸筋が動員されます。
これらは、本来呼吸以外の動作に関与する筋ですが、胸郭を持ち上げる力を持っているため、吸気を助ける作用があります。
代表的な補助呼吸筋には以下のようなものがあります:
- 胸鎖乳突筋:頸部を伸展させつつ、胸郭上部を持ち上げる
- 斜角筋群(前・中・後):第1・2肋骨を挙上する
- 小胸筋・大胸筋:肩甲骨の固定により胸郭を拡張
- 僧帽筋:頸部後面から胸郭にかけて補助的に関与
補助呼吸筋の過度な使用は、努力呼吸のサインです。
例えば、慢性呼吸不全患者や急性呼吸窮迫症候群(ARDS)では、これらの筋が過剰に動員され、肩や頸部が上下する呼吸(肩呼吸)を呈します。
また、小児や高齢者では補助筋の使用を代償できないため、早期に呼吸不全に陥ることもあります。
また上記に挙げた補助呼吸筋は吸気時に働きますが、より努力呼吸が強まると呼気時にも以下の筋に収縮を認めます。
- 内肋間筋
- 内腹斜筋
呼吸筋の働きと呼吸仕事量
呼吸筋がどれだけ活動しているかは、呼吸仕事量(work of breathing)に直結します。
呼吸仕事量が増える状況とは、つまり「呼吸筋が無理をしている」状態です。
例えば、以下のような状態では呼吸仕事量が増加します:
- 気道抵抗の増加(COPD、喘息)
- 胸郭可動性の低下(拘束性疾患)
- 呼吸回数の増加(代償的頻呼吸)
- 筋力低下や疲労(ICU-AWなど)
こうした負荷が続くと、呼吸筋の疲弊によって呼吸停止に至ることもあります。
そのため、呼吸筋の動員状況を観察することが、呼吸不全の兆候を見抜くカギになります。
胸郭の動きと換気メカニズム
肺そのものには筋肉がないため、自ら動くことはできません。
肺を拡張・収縮させる力の源は、胸郭の動きです。つまり、胸郭がうまく動いてこそ、肺に空気が入り、酸素を体内に取り込むことができます。
胸郭の基本構造と可動性
胸郭は、肋骨・胸骨・胸椎で構成される骨性の“かご”のような構造です。
その内部に肺と心臓を収納しており、吸気時にこのかごが広がることで、肺が引き伸ばされ、空気が流れ込む仕組みです。
呼吸時には、肋骨が持ち上がるように動き、胸郭の前後・左右方向の容積が変化します。
この運動は、呼吸筋(横隔膜や外肋間筋)との協調動作によって実現しています。
バケットハンドルモーションとポンプハンドルモーション
胸郭運動は、大きく2つの動きに分類されます。
1つ目がポンプハンドルモーション(Pump Handle)です。
これは、胸郭前後方向の拡大で、主に上位肋骨(第2〜6肋骨)が持ち上がる動きです。
胸骨が前方に突き出すような運動で、胸式呼吸の主体となります。
2つ目がバケットハンドルモーション(Bucket Handle)です。
これは、胸郭側方(左右)方向の拡大で、中〜下位肋骨が持ち上がり、バケツの持ち手のように外側へ広がります。
これは横隔膜の収縮に伴って生じやすく、腹式呼吸の要素を含みます。
この2つの動きが同時に起こることで、胸郭全体の容積が増加し、肺に陰圧が生じて吸気が起こるのです。
呼吸様式:胸式呼吸と腹式呼吸の違い
呼吸の様式には、主に胸式呼吸と腹式呼吸があります。
- 胸式呼吸:外肋間筋を中心とした動きで、胸郭が上下・前後に動く
- 腹式呼吸:横隔膜を主に使い、腹部の膨張として観察される
安静時の正常な成人では、腹式呼吸が優位であることが一般的です。
しかし、疼痛・疲労・呼吸筋障害などがあると、胸式呼吸に偏ることがあり、非効率な換気になることもあります。
また、呼吸リハビリテーションでは、これらの様式を評価し、適切に誘導することが重要な介入になります。
姿勢と体位が与える胸郭への影響
胸郭の動きは、姿勢や体位によって大きく影響を受けます。
- 仰臥位では横隔膜が押し上げられ、可動性がやや制限される
- 座位や立位では重力の影響で肺底部の換気が促進されやすい
- 側臥位では下側の肺の換気が良くなる(体重と重力の影響)
また、脊柱のアライメント(猫背・側弯など)や、胸郭の柔軟性が低下していると、呼吸効率にも悪影響を及ぼします。
そのため、呼吸リハビリテーションでは体位ドレナージや体幹柔軟性の改善が重要となります。
胸郭の動きが制限されれば、肺の拡張も制限されます。
つまり、胸郭の動きを観察することは、「肺にどれだけ空気が届いているか」を把握するための重要な視点です。
安静呼吸と努力呼吸の違いを見抜く
呼吸には、通常の穏やかな呼吸(安静呼吸)と、身体が強く酸素を求めているときの呼吸(努力呼吸)があります。
この2つを見極める力は、臨床の現場で灌流や呼吸の異常を察知するうえで極めて重要です。
「呼吸を観察する」というシンプルな行為の中に、呼吸生理と身体の緊急度が隠されています。
この章では、安静呼吸と努力呼吸の違いを構造・動き・観察ポイントの視点で整理していきます。
安静呼吸とは|自律的に行われるエネルギー効率の高い呼吸
安静呼吸は、意識しなくても脳幹の呼吸中枢によって自動的に制御されている呼吸です。
横隔膜を中心とした動きで、わずかな陰圧によって肺を拡張させ、空気を取り込みます。
このときの呼吸筋の主な構成は:
- 吸気:横隔膜、外肋間筋
- 呼気:基本的には筋活動なし(受動的な弾性収縮)
安静呼吸の観察では、胸や肩が大きく動かず、腹部が穏やかに膨らんでいることが特徴です。
この状態では呼吸に大きなエネルギーは必要なく、最も効率的な換気が行われています。
努力呼吸とは|酸素需要の高まりによる代償的な呼吸
努力呼吸は、身体が「酸素をもっと必要としている」状態で現れます。
運動時や、病的な状態(肺炎・喘息・ARDS・貧血など)では、呼吸筋の活動が増強され、補助呼吸筋が動員されます。
特徴としては:
- 吸気に胸鎖乳突筋・斜角筋・大胸筋などが使われる
- 呼気にも腹筋群(腹直筋・外腹斜筋)が活動し、強制的に息を吐き出す
- 肩の上下動や頸部の張りなど、視覚的に明らかな努力が見られる
このような努力呼吸は、呼吸仕事量(Work of Breathing)が増しているサインです。
長時間続けば筋疲労や呼吸停止のリスクも高まり、早期の介入が求められます。
観察すべき臨床ポイント
安静呼吸か努力呼吸かを見抜くために、以下のようなポイントを観察します:
- 呼吸数(頻呼吸か?)
- 呼吸様式(腹式 or 胸式)
- 胸郭や肩・頸部の動き(補助筋の使用)
- 吸気と呼気の時間比(I:E比)
- 鼻翼呼吸や口すぼめ呼吸の有無
- 会話時の息切れ、会話の途切れ
特に「呼吸数」や「吸気にかかる時間」が長くなると、拡散障害や肺のコンプライアンス低下を示唆する場合があります。
また、吸気時に胸郭が陥没するような動き(奇異性呼吸)は、深刻な呼吸筋疲労を意味します。
努力呼吸は、身体が呼吸で「限界を迎えつつある」ことを教えてくれるサインです。
臨床では、こうしたわずかな動きの変化から、呼吸状態・灌流状態の悪化を早期に察知することが求められます。
まとめ|構造と運動から呼吸を評価する視点
ここまで解説してきたように、呼吸は「構造」と「運動」が密接に連携して成り立っています。
空気の通り道である解剖学的構造と、それを動かす筋肉や胸郭の運動の両方が整って、はじめて十分な換気が可能となります。
もしどこか一つでも破綻すれば、肺に空気が届かず、ガス交換が不十分になり、灌流の出発点が崩れることになります。
それは、組織酸素供給(DO₂)を低下させ、代償的な頻呼吸や努力呼吸、さらには循環への悪影響をもたらします。
そのため臨床では、「SpO₂が下がってから」対応するのではなく、
もっと手前の段階で“呼吸の異変”に気づける観察眼を持つことが重要です。
呼吸を観察するときの視点チェックリスト
以下のような項目を、評価・観察の軸として持っておくと、病態の変化や介入の効果を敏感に捉えることができます。
- 呼吸数とリズム:頻呼吸、無呼吸、吸気延長の有無
- 胸郭の動き:左右差、奇異性呼吸、胸部と腹部の同調性
- 呼吸筋の動員状況:肩や頸部が大きく動いていないか
- 呼吸様式:腹式か胸式か、体位で変化があるか
- 体勢の影響:仰臥位で呼吸が浅くなっていないか
- 呼吸の主観的負荷:会話の持続、表情、使用筋の緊張度
これらを「なんとなく」ではなく、構造と力学の裏づけをもって観察することで、より正確な判断と介入が可能になります。
灌流評価の第一歩としての呼吸評価
灌流を評価すると言うことは、心拍数や血圧、尿量なども重要です。
しかし実際には、そのすべての前段階にあるのが「呼吸」であり、酸素を取り込むため大きな柱です。
呼吸がうまくいっていなければ、どれだけ血液が流れても酸素は届きません。したがって、呼吸を“灌流の入口”として捉える視点を持つことが、臨床における観察力の質を一段引き上げてくれます。
呼吸編②では、
呼吸によって取り込まれた酸素が、肺胞でどのように血液に取り込まれ、灌流へとつながるか(換気血流比・拡散)について解説していきます。
ここまでの基礎編で得た「構造」と「動き」の理解が、次章以降のガス交換の理解と病態把握につながります。