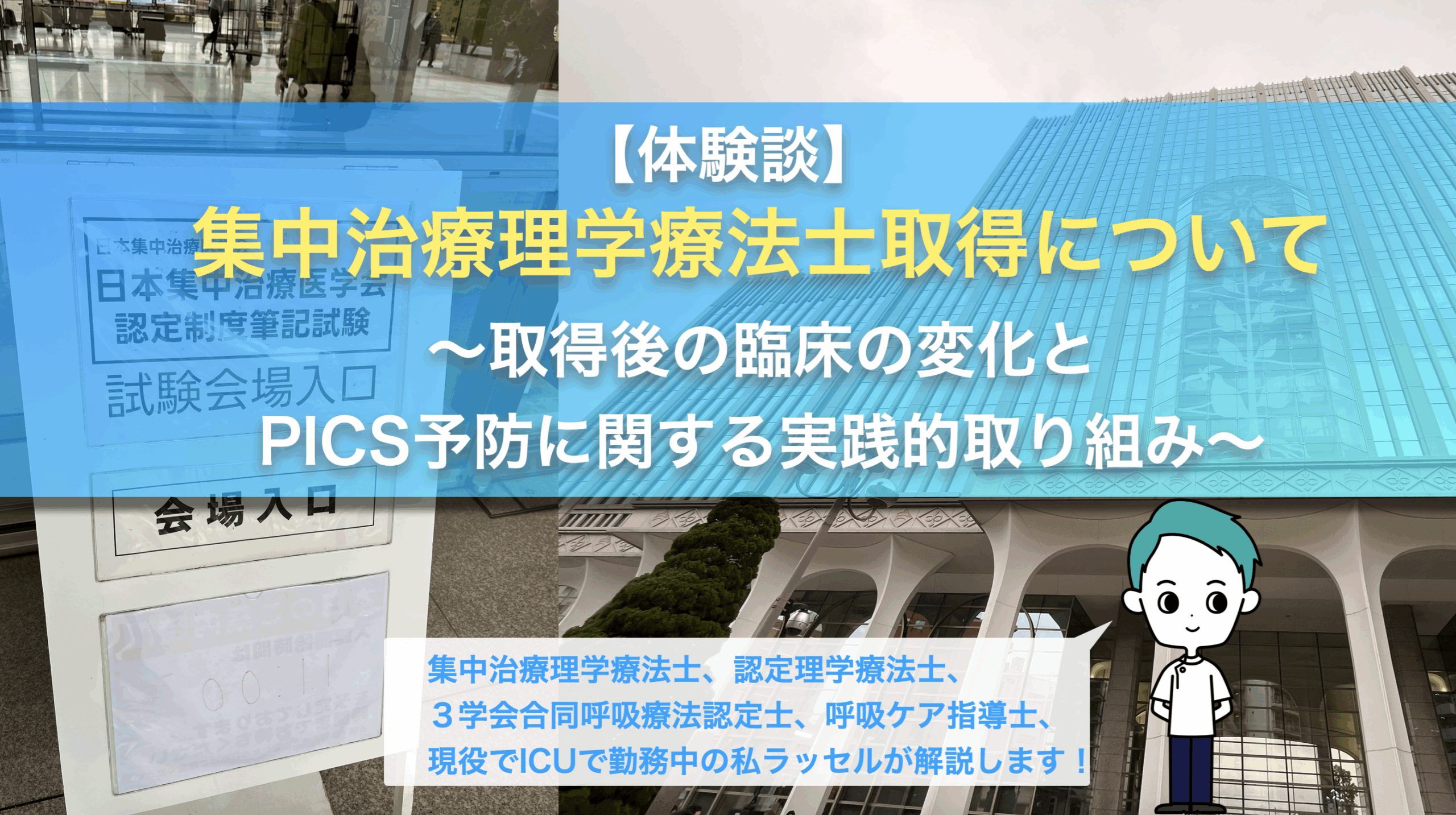この記事では、集中治療理学療法士の資格を取得した私、ラッセルが、資格取得に至るまでの流れや、その中で考えたこと・感じたことをまとめています。さらに、取得後に臨床でどのような変化があったのか、そして現在取り組んでいる活動についてもご紹介します。
集中治療理学療法士という資格は、決して簡単に取得できるものではありませんが、学びや経験を通じて得られるものは臨床の力となり、患者さんやご家族へのサポートの質を高める確かな手応えがあります。
この記事を読むことで、集中治療理学療法士を取得することの意義やメリットを具体的にイメージしていただけると思います。もし少しでも興味を持たれた方は、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。
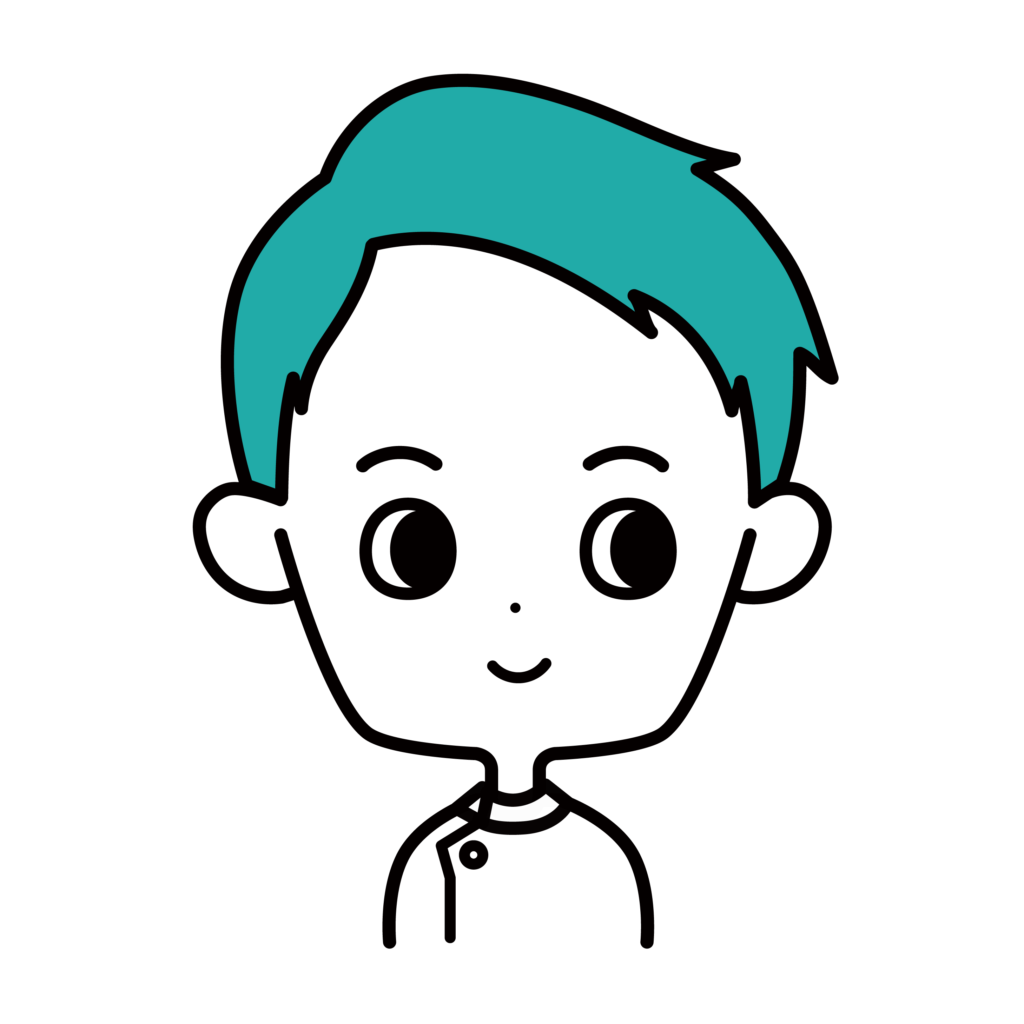
- 臨床19年目の現役理学療法士
- 認定理学療法士(呼吸)、集中治療理学療法士、3学会合同呼吸療法認定士、呼吸ケア指導士
- 集中治療室、救命救急病棟、一般病棟にて呼吸器疾患、重症疾患患者さんの治療に日々奮闘中
- 医療の最前線から本当に必要な情報を発信します
集中治療理学療法士との出会い
私はこれまで、急性期病院で呼吸リハビリテーションを中心に臨床を積み重ねてきました。ICUを含む重症患者さんと関わる機会は多く、日々の治療を通じて「どうすればより良い回復につなげられるのか」と自問する毎日でした。
特に大きな転機となったのは、コロナ禍の初期に対応した重症患者さんたちです。人工呼吸器管理下でのアプローチに加え、ECMOを装着している患者さんへのリハビリテーションを経験したことは、臨床の限界と可能性の両方を突きつけられる体験でした。リスク管理や負荷量の調整に細心の注意を払いながら、チームで少しずつ前進させる日々。その中で「もっと集中治療領域を深く学びたい」という思いが芽生えました。
以前から研修会等でご講演を聞かせていただく理学療法士協会の重鎮の先生から、集中治療に特化した資格の創設についてはぼんやりですがお話しを聞いていました。そんな前情報がありながらも参加した集中治療医学会で、「集中治療理学療法士」という新しい資格が創設されることを知りました。まだ立ち上がったばかりの制度で、未知な部分も多い資格でしたが、だからこそ「自分が挑戦することでパイオニアの一人になれる」と感じました。これまで培ってきた経験をさらに深め、活かすための大きな一歩になると考え、取得を決意したのです。
資格取得までの道のり
集中治療理学療法士の取得には、臨床経験だけでなく明確な要件が定められています。まず、一定年数の現場経験を積むことが必須です。そのうえで、学会への参加や集中治療分野での症例報告の提出を行い、最終的には筆記試験を受ける流れとなります。
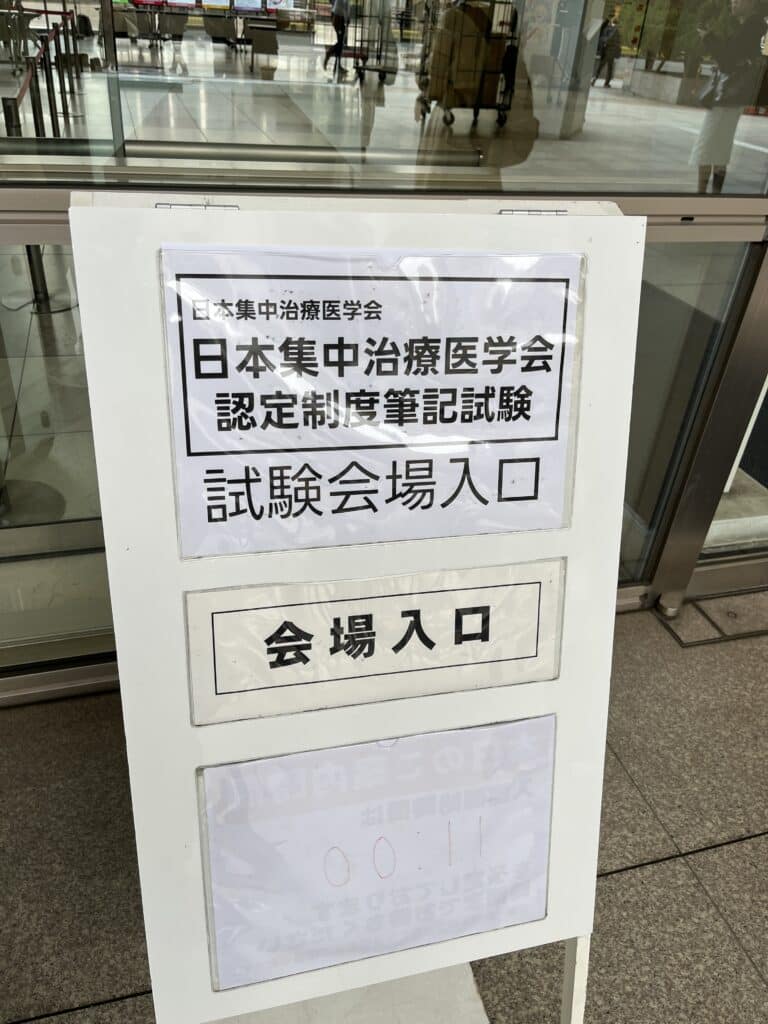
実際に準備を始めてみると、その内容は想像以上に幅広く、かつ専門的でした。これまで学んできた「認定理学療法士」や「三学会呼吸療法認定士」と比較しても、必要な知識の範囲は広く、より深い理解が求められました。
筆記試験はこれまでの試験の中で一番手応えがなかったです…
日々の臨床業務をこなしながら勉強時間を捻出するのは簡単ではなく、さらに家庭や育児との両立も加わり、正直に言えば大変な時期でした。しかしその過程は、自分の知識や臨床の引き出しを改めて整理し直す機会ともなりました。苦労はあったものの、「学び直す」というプロセスを通じて、集中治療領域で必要とされる考え方やエビデンスに基づく実践力を一つずつ積み重ねることができたのです。
資格取得後に見えたもの
資格を取得した後、臨床に対する視点は大きく変化しました。特に、重症患者さんに起こり得る障害像がより明確になり、理学療法士として「自分は何を成すべきか」という役割をはっきりと意識できるようになったのです。
その中でも重要なのが PICS(Post Intensive Care Syndrome:集中治療後症候群) の予防です。PICSは急性期を乗り越えた後も患者さんに身体的・精神的・認知的な障害を残し、長期的な生活の質を大きく損なう可能性があります。集中治療理学療法士として学んだことで、この課題に対して理学療法士が積極的に関わる必要性を強く実感しました。
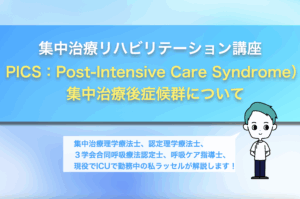
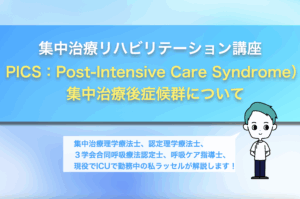
また、PICSを含む重症患者リハビリに取り組むには、理学療法士だけの力では不十分です。多職種での連携が必須であり、そのために共通言語としての専門知識が欠かせないということを、学びを通じて痛感しました。医師や看護師、薬剤師、管理栄養士など、それぞれの職種が持つ専門性を理解し、同じ基盤の知識を共有することで、ようやく「本当の意味でのチーム医療」が実現していきます。
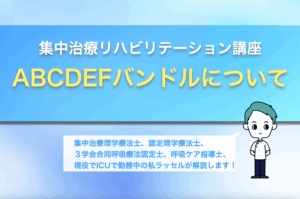
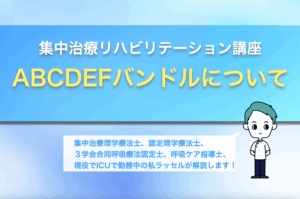
集中治療理学療法士として得られた知識や考え方は、私にとって単なる資格以上のものであり、臨床の中で「より明確な責任と役割」を持つことにつながっています。
臨床で活きている学び
資格を取得してから、日々の臨床の現場で活きていると感じることがいくつもあります。特に大きな変化は、早期離床を実践する際のリスク管理や負荷量の判断を、より根拠をもって行えるようになったことです。
重症患者さんに対しては、わずかなアプローチが大きな影響を及ぼすことがあります。以前は経験則に頼る部分も多かった判断が、学びを通じて理論的に裏付けられ、安心して介入できるようになりました。その結果、「やりすぎず、やらなさすぎず」というバランスを意識しながら、患者さん一人ひとりに最適な運動療法を提供できるようになったと感じています。
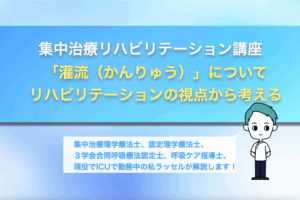
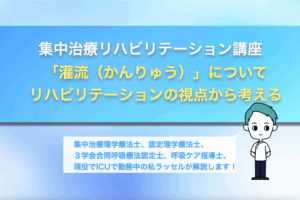
また、資格取得で得た知識は、患者さんやご家族への説明にも直結しています。例えば「なぜ今この程度の運動負荷なのか」「どのように回復を見込んでいくのか」といった説明を、より具体的に、かつ分かりやすく伝えられるようになりました。これは患者さんや家族の安心感につながり、信頼関係の構築にも大きな役割を果たしています。
こうした日常臨床での積み重ねこそ、資格取得の学びが実を結んでいることを実感する瞬間です。
現在取り組んでいる活動とこれから
資格を取得して終わりではなく、現在も臨床の現場で新しい取り組みを続けています。
その一つが PICSラウンド です。
PICSラウンドとは、ICUを退出した患者さんを対象に、多職種で構成されたチームが一般病棟をラウンドし、フォローアップを行う取り組みです。集中治療後症候群(PICS)はICU退出後により顕著に現れることが多く、身体機能障害、精神障害、認知機能障害といった問題が患者本人に生じます。さらに特徴的なのは、患者さんのご家族にも精神的な不調が生じることが知られている点です。そこで、患者本人や家族に身体的・精神的・認知的な問題がないか、日常生活やQOLに支障をきたしていないかを多職種チームで評価することを目的として実施しています。
このPICSラウンドを立ち上げ、現在は実際に臨床現場で運用を開始しました。まだ走りながら改善を加えている段階ですが、最終的には成果をまとめ、より良い形で定着させていきたいと考えています。
さらに、PICS自体の認知度を高める活動にも取り組んでいます。まずはリハビリテーション部内で勉強会を開催し、スタッフの理解を深めることから始めました。その後、看護師や医師をはじめとする多職種を対象にした院内勉強会も企画・運営し、PICSを共通の課題として広める取り組みを進めています。
PICSは急性期だけでなく、回復期・生活期にまで影響が及ぶ重要なテーマです。だからこそ、理学療法士が主体的に啓発を担い、多職種と協力しながら継続的に取り組んでいく必要があります。
集中治療理学療法士として得た学びや経験は、臨床に直結するだけでなく、こうした活動を推進する原動力にもなっています。今後も仲間と共に知見を広め、質の高い医療の実現につなげていきたいと思っています。